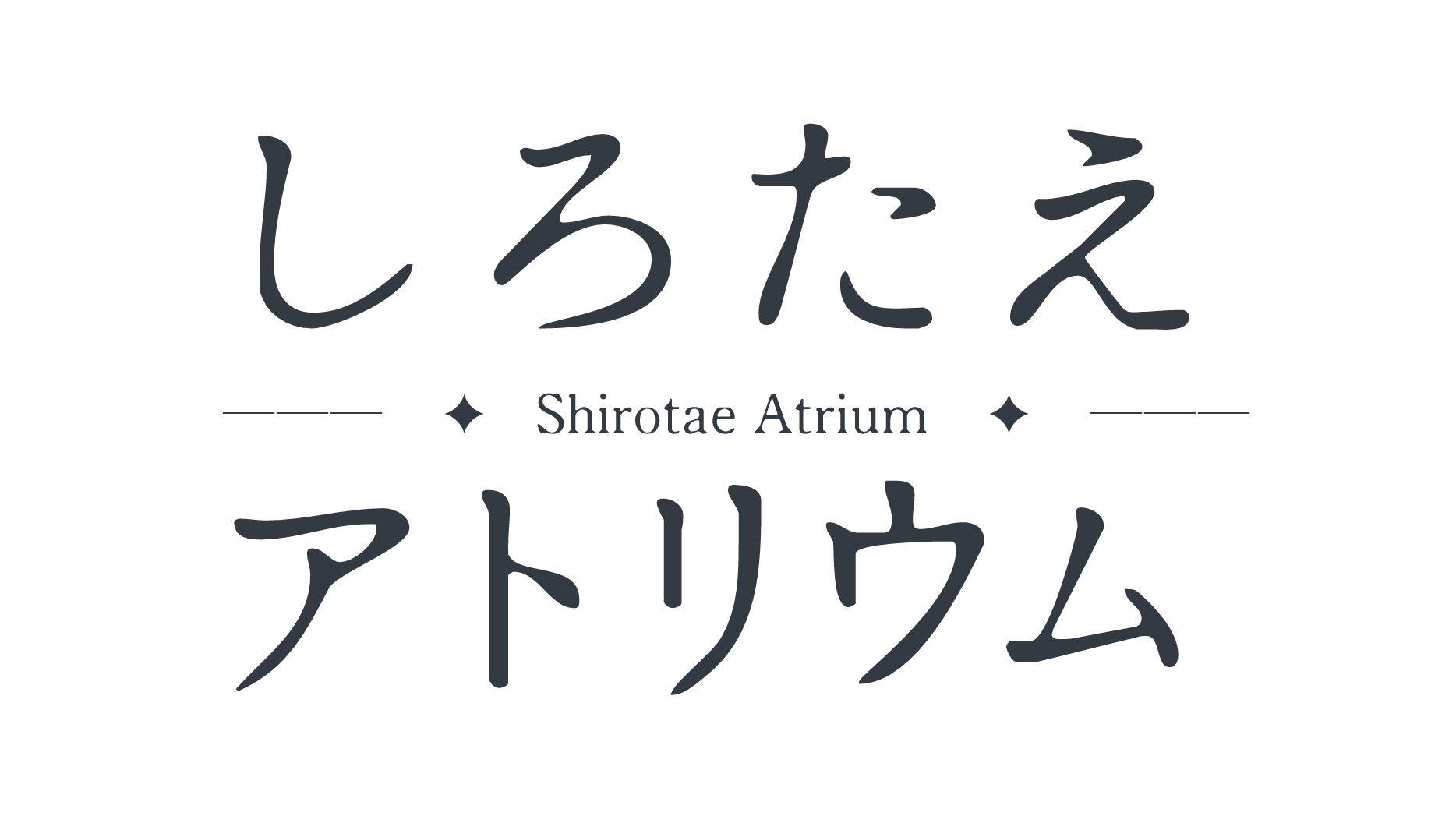✦
棚の上で鈍くまたたきを返す銀の飾り箱。そこに、妻が今でも眠っている。
葡萄の蔦と房が繊細にあしらわれた、銀細工の箱。
確か妻が母方の祖母から受け継いだもので、それより前の逸話のことを彼は知らない。ありふれた既製品なのか、由緒あるものなのか、それさえ分からない。知っているのはただ、妻がその箱をつよく所望して譲り受けたということだけだ。
少女の時分の妻にとって、その銀箱はそれそのものが宝だったのだという。細く優美な脚をもつその箱は、確かにとても美しい。けれど妻がそうまで言うのでなければ、男はきっと目にも留めなかった。元来、道具など本来の機能さえ果たされていればそれでいい。それでもその箱を美しいと感じるようになったのは、妻が愛し、思いをかけて大切にし続けたものだからだ。あれは妻の物語のひとつであり、美しい枝葉であり、闇夜にまたたく星のようなものだ。
男にとって、手の届かぬ星などひと匙ほどの意味もなかった。けれど男は、夜空を見上げることをおぼえた。闇に穿たれた針穴に過ぎぬ星ぼしも、今は美しい飾り模様に見える。それはきっと、妻が星を愛する女だったから。
彼女の愛は果てもなく、すべてを愛していたように思われた。男にとっては無駄で酔狂としか思えないものまで、何もかも。
彼女が幸せそうであればこそ、男はその酔狂を黙って見守った。大事なのは彼女が幸せそうにしていることであって、彼女の好む妙な物品や事象の真価についてはいちいち問うことはしないことにしていた。
遠い昔、男自身の価値観で彼女の嗜好物に評を下したことはある。彼女はただ、「野暮なことを仰るのね、 それでも私には価値があるのよ」と言って笑うばかりだった。どんな理屈を並べ立てど、彼女の中に揺るぎのない価値がある。彼女は、それを愛した。ならば 解することのできない己にこそ、きっと未熟があるのだろう。彼女が喜ぶならそれを価値としようときめて、それきり論ずることはやめた。
妻はなにしろ壁に落ちる己の影にさえ価値を見出す女だったから、奢侈に財布を脅かすこともなかった。寡黙でいられないという欠点にさえ目を瞑れば――静寂を愛する男にとって、それは些か大き過ぎる欠点ではあったのだが――いたって無害な、幸せな女だった。
――彼女の幸せなお喋りがはたりと止んだのは、数年前の冬だった。
雪のしんしんと降る、つめたい夜。彼女は病で、あの夜まるで、灯火が消えるようにそっと消えてしまった。
彼女がいなくなって、驚いた。この小さな家は、驚くほどに広く、薄暗い。
彼女の笑い声も無邪気な抱擁も、この家を照らす灯火であり、闇夜の星灯りそのものだった。それを痛感する。
妻の遺した名残は、この家のそこかしこにあった。 彼女の服、対のカップ、銀食器、食卓布、棚の本、編み棒、探せばいくらでも。物に価値を見出さない男に比べ、妻は些細なものをいつまでも大切に残しておいてしまう女だった。生前は呆れて眺めたその品の数だけ、今はいなくなってしまったひとの面影を思い出す。
そんな品の中に、あの葡萄模様の銀箱はあった。
「あれは特別なの。宝箱だから、私のいるうちは開けてはだめよ」
妻は少女のように笑って、そう言ったものだった。
また戯れが始まったと思いこそすれ、男は別段とりあってやることもなかった。
彼女のその手の戯れは数えても数えても足りないほど無数にあったから、閑かさを愛する男にとっては煩わしい瞬間さえあった。はいはい、わかったよ、というつれないこたえでも、彼女はたいして気にも留めなかった。彼女は彼女で、男のつれない返答には慣れていたように思う。
それでもその時は珍しく食い下がって、こう一言だけつけ加えて笑った。
「私がもし先にいなくなったら、見てもいいわ」
「遺書でも書いたのか」と問うと、彼女は「野暮ねえ」 と言って笑った。
――それを思い出したとき、亡き人の宝箱はかわらず棚の上でひっそりしていた。当たり前のようにそこにあり、日々のなかで視界にすら留まらなくなっていたそれ。その美しい葡萄細工を覆う埃は、あるじを失った時間を物語るようだった。
そっと表面をぬぐう。
一体、何をここに守っていたのだろう?
妻はもういない。それなのに、妻の戯れだけがここに眠っている。それがあまりに不思議でならなかった。
銀箱に閉ざされた空気は、彼女がまだ生きていた時分のものだろう。それを外気に触れさせるのも、どことなく憚られた。妻はここにまだ在るのかもしれないのに。
それでも男は、そっと箱を開いた。
いちばん上にかさねられた、花模様のちいさな紙札。
そこに踊る、彼女のなつかしい文字のさざめき。
『親愛なるあなたへ
あなた、いつも私の戯言を取りあってくださらないでしょう。
私は知っているのよ、照れ屋な旦那さま。
きっと私がいない時の方が、素直にこちらを見てくださるでしょう?
だからこの手紙を綴りました。
返事は照れるでしょうから要らないわ、
でもちゃんと読んで下さる?
親愛なる旦那さまへ、愛を込めて』
――手紙だった。
紙札の下に眠っていたのは、
何通も、何通も、何通も重ねられた手紙の束だった。
日にやけることなく美しい白の便箋。
無骨な手でおそるおそる触れれば、かさりと音を立てる。
静寂に、時計の針の刻む音。
おどるような彼女の文字は、ただ男への感謝を綴っていた。
取るに足らないささやかなことを、なんでもないようなことを、いちいちすくい上げて。
私の行為は、そんな大それた価値などないのに。
彼女をまともに取り合わなかった己を悔いながら、霞む目を拭う。
つれない私に、返事のかえらぬ手紙を――読まれすらしないかもしれぬ手紙を、おまえは一体どんな思いで綴ったのだろう。おまえに何ひとつ返せなかった私に。
けれど亡き妻は、しっかりと釘を刺すことを忘れない。
『ご自分のしたことに大層な価値はないと、あなたはお言いかしら』
そう。男にとっては、すべてとるに足らぬことだった。深い含意などなにひとつない。ただ闇夜に穿たれた穴にすぎない。
それでも。
『だけどお生憎さま、
――それでも私には価値があるのよ』
彼女はそれを、美しい星灯りのように愛した。
彼女はいない。もうどこにもいない。
それでも妻の名残が、彼女が愛したあらゆる物事が、男の世界をほの明るく照らす。
妻は、今でもそこに眠っているのだ。
美しい銀箱のなかに、星降る夜のなかに、彼をつつむ全てのなかに。
いつかのように、悪戯げに笑って。
随分ばかばかしい詩的な感傷だと、男はひとり笑う。
野暮ねえ、と妻が笑う声を聞いた気がした。
✦